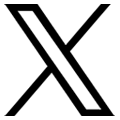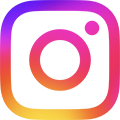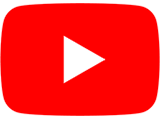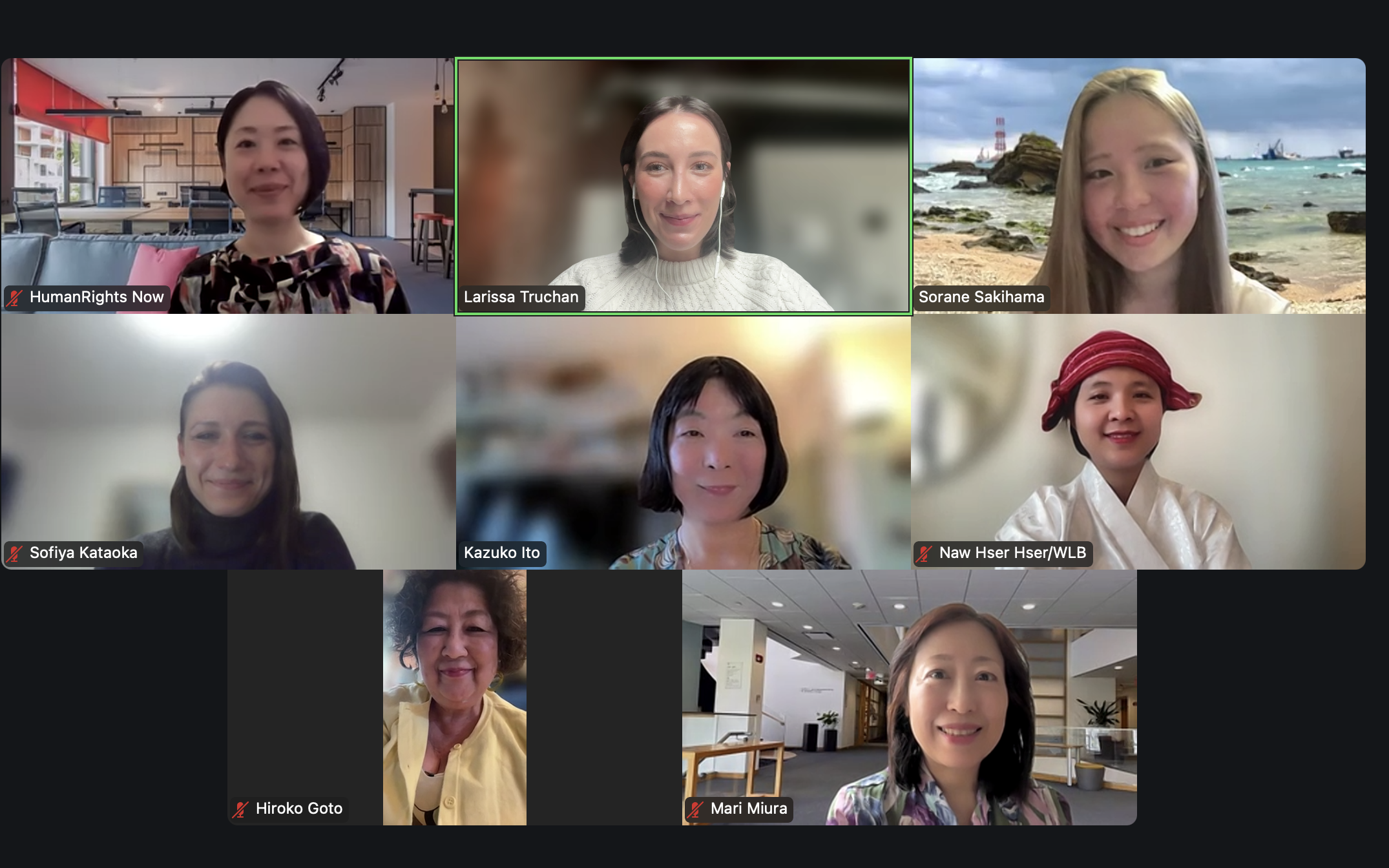☆本イベントの録画はこちらからご覧いただけます☆
2025年3月12日、CSW69(第69回国連女性の地位委員会)開催中に、ヒューマンライツ・ナウは、「武力紛争の影響を受ける女性の視点からの平和構築」と題したオンラインイベントを開催しました。
武力紛争・軍事占領における人権侵害は、民間人に大きな犠牲を強います。生きる権利が脅かされるだけでなく、少女や女性は性的暴力の標的にされる危険にも晒されるリスクが高く、その影響や被害は平和が訪れた後も続きます。本イベントでは、北京宣言と行動綱領採択30周年、国連安保理決議1325号採択25周年、そして第二次世界大戦終結80周年を記念し、戦後80年を経た今もなお原爆の後遺症に苦しむ女性たち、米軍基地のある沖縄で米兵による性暴力の脅威に晒されている女性たち、ウクライナやミャンマーなど現在も続く武力紛争の中にいる女性たちの置かれた現状に光を当てました。また、過去の教訓を共有することで、北京宣言の中核目標のひとつである 「すべての女性のための平和の進展 」の達成への道筋について考えました。そして、「正義と説明責任、そして意思決定への女性の参画なしでは真の平和は実現できない」ことを明確にしました。
開会の挨拶
HRNユース国連代表のLarissa Truchanは、冒頭の挨拶で、女性は紛争における受動的な被害者ではなく、平和構築への積極的な参加者であることを強調しました。この議論は、「女性・平和・安全保障に関する国連安全保障理事会決議1325号」の採択25周年と、「北京行動綱領」の採択30周年に触発されたものです。
また、HRNを代表して、第63回社会開発委員会(CSocD63)、国連総会議長との市民社会のタウンホール、核兵器禁止条約 (TPNW) 第3回締約国会議などで平和と安全保障に関する懸念を表明したHRNの2025年の活動についても紹介しました。
片岡ソフィア氏
片岡ソフィア氏は、ウクライナのキエフで生まれ、日本でNPO法人日本ウクライナ友好協会(KRAIANY)の理事を務めています。本イベントでは、100年以上にわたるロシアの長期的な侵略について説明し、この長期的な侵略が彼女と家族にどのような影響を受けたかを共有しました。2014年以来、本格的な侵略が始まり、活動家たちが殺され、秘密裏に埋葬される集団墓地や拷問室、大量虐殺の武器として使われる女性や少女の組織的にレイプが起こりました。さらに、2万人以上のウクライナの子どもたちが拉致され、ロシアに強制送還され、家族から永遠に引き離される事態が続いています。爆撃によって家や学校、病院が破壊され、数百万の人が貧困にあえぎながら避難生活を強いられています。片岡氏は、ロシアのいわゆる「和平計画」は交渉ではなく、ウクライナを消し去ろうとするものであり、個人が戦争犯罪に対して責任を負うべきだと強く訴えました。
Naw Hser Hser氏
Naw Hser Hser氏は、ビルマ女性連盟(Women’s League of Burma)のアドボカシー代表であり、母体であるカレン女性組織(Karen Women’s Organization:KWO)のメンバー・アドボカシー・ディレクターも務め、アジア太平洋女性法開発会議(Asia Pacific Women, Law and Development:APWLD)の元地域評議員を務めました。2012年から2021年にかけてのミャンマーの軍事クーデターが、特に女性や子どもに対して、どのように性的暴力が戦争の武器として利用されてきたかを強調しました。また、和平プロセスにおける家父長制の性質が、適切な女性代表を排除してきたことにも言及しました。この状況は、アメリカが最近行った資金削減によってさらに悪化しています。以前は生存者を支援するために法律援助、基本的な生活支援、リハビリテーションが提供されていましたが、それらの支援が減少したことが影響しています。
継続的な努力の結果、女性の和平交渉への参加率は25.5%まで増加しました。しかし、少なくとも30%を目指しているものの、持続可能な平和と正義を実現するためには、さらに多くの女性の参加が必要だと述べました。
崎浜空音氏
慶應義塾大学法学部の学生で、沖縄出身の若い女性である崎浜空音氏は、1972年以降、沖縄で米軍関係者によって行われている性犯罪や誘拐、殺人などの暴力や不正義について話しました。崎浜氏は、13歳から現在の23歳まで、祖父母や沖縄の上の世代の方々が、「もう繰り返さない、子や孫のために闘う」と約束し、集会や抗議行動で闘う姿を目撃してきたと語りました。しかし、こうした努力があるにもかかわらず、性暴力事件は後を絶ちません。2023年には沖縄米兵によるレイプ事件が県に共有されない事件も発生しました。崎浜氏は、沖縄が依然として日本の保護下にあることを認める特権の承認、米軍関係者が日本で訴追されることを防ぐ1960年の日米地位協定(SOFA)の改正、そして占領地の女性を守るために、日本本土や世界各国での意識向上と情報共有の拡大が必要だと緊急性を訴えました。
田中稔子氏(ビデオメッセージ)
広島の被爆者である田中稔子氏による力強いビデオメッセージは、核被害者が長年にわたって抱えてきた苦しみを浮き彫りにしました。大量の死傷者や放射線による病気といった原爆の恐怖に加え、女性たちは社会的、精神的、肉体的に深刻なトラウマを受けました。また、がんや先天性異常、精神的な問題、生殖に関する健康問題などによって、被爆者たちは社会から排除され、汚名を着せられるという苦しみが語られました。田中氏は、核兵器禁止条約(TPNW)を通じて、核兵器のない世界への希望を表明し、私たちは今こそ共に行動しなければならないと訴えました。
閉会の辞 (HRN副理事長 伊藤和子)
閉会の辞で、HRN副理事長の弁護士である伊藤は、1995年の北京女性会議への参加を振り返り、国際的に認められているにもかかわらず、法の支配や人権、正義、説明責任、そして女性の参加が尊重されないまま、紛争交渉はほとんど進展していないことが指摘されました。伊藤は、「危機の時代」と世界の核兵器への執着に終止符を打つよう、以下の点を訴えました。
・ガザ地区の女性たちを想い、連帯すること。
・ウクライナ、ミャンマー、沖縄、そして広島で、平和構築の最前線に立つ女性を認識すること。
・加害者の責任追及を含め、国連の指導の下、平和と人権政策への女性の参加を支援すること。
また、私たちが共にできることとしては、以下を強調しました。
・意識を喚起し、これらの物語を共有するー沈黙は加担である。
・和平交渉に女性を参加させるための政策変更を要求する。
本ウェビナーを通して発信された「女性の声は必要であるだけでなく、恒久的な平和の鍵である」というメッセージを真摯に受け止め、できることを実行に移していくことの重要性を再認識させられるイベントとなりました。
パネリストのプロフィール
田中稔子氏
広島市東区在住の被爆者で、壁面七宝作家としても知られている。1945年8月6日、6歳のときに広島市牛田地区で爆心地から約2.3kmの場所で被爆。右腕や頭、首に火傷を負い、放射線の影響による健康被害にも苦しめられた。その後、戦後の困難を乗り越え、核兵器廃絶を訴える活動を続けている。ピースボートの地球一周航海にも複数回参加し、世界各地で講演を行うなど、核廃絶のメッセージを世界中に発信している。
Naw Hser Hser氏
ビルマ女性連盟 (Women’s League of Burma) 前事務局長。現在、ビルマ女性連盟の政治イニシアティブ・アドボカシー代表。ビルマ全国統一協議会(National Unity Consultative Council, NUCC)におけるビルマ女性連盟代表の一人でもある。また、母体であるカレン女性組織(Karen Women’s Organization, KWO)のメンバー・アドボカシー・ディレクターも務めているほか、2020-2023年にはアジア太平洋女性法開発会議(APWLD)の地域評議員も務めた。アジア太平洋緊急行動基金(Urgent Action Fund – the Asia Pacific)の諮問委員でもある。
2019年には、カレン民族同盟(KNU)の代表団として、21世紀パンロン和平会議に参加した。会議中、政治部門でNCA-EAOs代表団を率いて、ジェンダー平等と意思決定プロセスの全レベルにおける女性の参加を提唱した。2015年から2017年には、KNUの和平プロセス参加のための技術支援チームも務めた。
2008年にカレン女性組織(Karen Women’s Organization, KWO)に加わって以来、15年以上にわたり、人権、女性の権利、正義、説明責任、不処罰制度の廃止を提唱してきた。また、民族の平等と自決を提唱し、カレン州内だけでなく、国内、地域、国際レベルの政治プロセスにも参加してきた。その献身的な活動が認められ、2018年にファン財団 (phan foundation) からプドー・マーン・シャー・ラー・ファン・カレン・ヤング・リーダー賞を受賞した。
片岡ソフィア氏
1993年に家族で来日して以来、日本を故郷としている。NPO法人日本ウクライナ友好協会(KRAIANY)の理事として、ウクライナの現状をより深く正確に理解するための活動を積極的に行っている。特に、負傷者のリハビリ支援や、救急車などの医療物資をウクライナに送るプロジェクトに力を入れている。
NPO法人KRAIANYは、日本とウクライナの文化の架け橋となる連帯と支援の光。ウクライナの文化、歴史、時事問題に対する日本国内での理解を深めることを使命としている。文化交流にとどまらず、困難な状況にあるウクライナを支援する人道的な活動にも積極的に取り組んでいる。ロシアの侵攻で被害を受けた人々へのリハビリ支援、必要不可欠な医療品や医療機器の送付、ウクライナで子どもたちが安全に教育プログラムを続けられるよう防空壕を建設するなどの取り組みも行っている。
崎浜空音氏
2002年沖縄県北谷町生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科在籍。2021年度、2022年度に外務省TOFUプロジェクトに参加し2023年に訪米。2024年1月と11月に沖縄県主催トークキャラバンで玉城知事と登壇。2024年12月に開催された米兵による少女暴行事件に対する抗議と再発防止を求める沖縄県民大会でスピーチを行う。主に、沖縄戦や基地問題、選挙に関する情報をSNSで発信。
モデレーター :Larissa Truchan(HRN ユース国連代表)
コメンテーター :伊藤和子(HRN副理事長/弁護士)