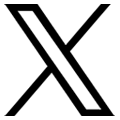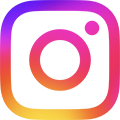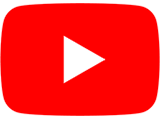☆本イベントの録画はこちらからご覧いただけます☆
2024年10月、国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)による審査が8年ぶりに実施され、11月には委員会から日本政府に対する勧告を含む総括所見が発表されました。委員会勧告で指摘された課題には、選択的夫婦別姓、政治・経済分野の男女格差、セクシュアル・リプロダクティブヘルス・ライツ、福島原発事故の被災者、沖縄における性暴力、マイノリティ女性の直面する課題など、日本社会が解決すべき喫緊の課題が多く含まれています。あらゆる分野において国際人権基準から遅れた日本の現状と、国連勧告への政府の誠意を欠く対応は、多くの人権課題の根本的原因であり、一日も早く委員会の勧告を履行し、現状を改善する必要があります。
本ウェビナーでは、元国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)委員・委員長を務められた林陽子氏をお迎えし、CEDAW勧告の概要や意義、審査で問われた日本の課題、日本政府の対応の問題点についてお話し頂きました。また、選択的夫婦別姓、性と生殖に関する健康と権利、福島原発事故などについても、審査に関わったNGO関係者から発言をいただき、CEDAW勧告をどう受け止め、私たちがこれをどう生かしていくべきか、についてお話し頂きました。
【登壇者】
林陽子氏
弁護士。元国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)委員(2008-2018 )、同委員長(2015-2017)。G7ジェンダー平等諮問会議委員(2018-2019)。(公財)市川房枝記念会女性と政治センター理事長(2023-現在)。
井田奈穂氏
一般社団法人あすには代表理事。企業広報、ライターとしての活動の傍ら、再婚での改姓をきっかけに、2018年選択的夫婦別姓の法制化を目指す当事者団体を創立。2023年法人化し、現職。800人を超えるメンバー登録者、経済・法曹団体などと地方会議・国会への陳情活動を協働。2024年国連女性差別撤廃条約に基づく日本審査にNGOとして参加、4度目のより強い改善勧告につなげた。ForbesJAPAN「いま注目のNPO50」に選出。共著に「選択的夫婦別姓は、なぜ実現しないのか?:日本のジェンダー平等と政治」(花伝社)。
日本でのSRHR(性と生殖に関する健康と権利)実現を目指す#なんでないのプロジェクト 代表。2021年にヨーテボリ大学公衆衛生学修士号を取得後、国連人口基金ルワンダ事務所にて難民キャンプのSRHR推進に従事。現在は東京を拠点にSRHRアクティビストとして活動し、#緊急避妊薬を薬局でプロジェクト共同代表やFIFTYS PROJECT副代表も務める。2024年6月より東京大学多様性包摂共創センター特任研究員。
徳永恵美香
HRNメンバー
【要約】
開会の挨拶
HRN関西事務局長の雪田樹理より挨拶がありました。
林陽子氏(基調講演:CEDAWと日本について)
林氏よりCEDAWに関する説明があり、日本審査の内容や政府の対応についても触れられました。日本は1985年にCEDAW(女性差別撤廃条約)を批准し、2024年までに計6回の審査を受けています。この条約は、家族法の改正、均等法の制定と改正及び強化、刑法の改正、ジェンダーに基づく暴力の概念の確立、リプロダクティブヘルスライツ(性と生殖に関する健康と権利)の概念の確立など、日本に大きな変化をもたらしてきました。2024年10月のCEDAWの日本審査においては、女性差別の定義や直接・間接差別の禁止、差別を救助するための包括的な差別禁止法の制定、沖縄における米軍犯罪の不処罰問題、刑法における堕胎罪の廃止、妊娠中絶に対する配偶者同意の撤廃など、多岐にわたる課題が審査項目として挙げられました。
一方で、林氏は、日本におけるジェンダー平等の法整備が進まない現状についても指摘しました。その主な理由として、政策決定の場における女性の少なさや、内閣府男女平等参画局の動きの鈍さを挙げました。ジェンダー平等を推進するためには、「包括的反差別法」「国内人権機関」「個人通報制度」のトライアングルが相互に機能することが必要だと述べました。特に、建設的な対話の中で国内人権機関の役割が重要であり、また人権指標の高さと国内人権機関の存在には密接な関連性があると強調しました。更に、林氏は、地方議会ができることとして、女性差別選択議定書批准に向けた意見書の採択や、人権・ジェンダー平等に関連する条例の制定を提案しました。
井田奈穂氏(トピック:選択的夫婦別姓)
井田氏より、選択的夫婦別姓に関するCEDAW審査および勧告内容についてのお話がありました。井田氏は、世界中で選択的別姓が進められ実現している中で、日本だけが夫婦同姓を強制していることを指摘し、夫婦同性の強制が国連差別撤廃条約の第1条、第5条(a)、第8条、第11条(a)-(c)、第16条に違反していると強調しました。
CEDAW審査の中で、井田氏は、グループとして、家父長制度の影響を受けている夫婦同性の強制に対して日本政府に選択的夫婦別姓の導入を勧告し、さらにその後の措置について2年以内に文書で提出するよう求めました。しかし審査中、日本政府はどの質問にも同じ答えを繰り返し、旧姓使用の妥当性を主張し続けました。
結果として、CEDAWは、日本政府が民法750条の改正に向けた対策を何一つ講じていないことを指摘し、選択的夫婦別姓の導入と、2年以内に民法750条改訂のために取った措置についての文書報告を求めました。また、司法関係者に対するCEDAWに関する研修の実施や、家父長制に基づくジェンダーのステレオタイプへの懸念についても勧告しました。
これに対して、「あすには」の活動として、各党を回り勧告についての勉強会を開催したり、経済団体や士業団体とロビイング活動を行ったり、事実婚に関する全国調査を実施していることが紹介されました。
徳永恵美香(トピック:福島原発事故の被災者の権利)
徳永氏からは、福島原発事故の被災者の権利に関するCEDAW勧告についての説明がありました。福島原発事故による国内避難民の女性が直面している職業選択の制限、貧困、PTSDや不安障害などの精神的な問題、そして強制退居の現状について報告しました。
それに対して、CEDAWは、福島原発事故災害において女性、少女、女児が基本的人権を完全に享受し、実質的な平等が実現できるよう、社会的サービスや意思決定の機会に平等にアクセスできることを求め、暫定的特別措置の採用を勧告するという形で、日本政府に対応を求めました。
福田和子氏(トピック:性と生殖に関する健康と権利)
福田氏からは、さまざまな団体と共同で性と生殖に関する健康と権利(SRHR)に関する市民社会レポートを作成し、それをCEDAWに提出したこと、そして、SRHRに対するCEDAW勧告についての説明がありました。
教育・性教育の観点について、CEDAWは、セクシュアリティ教育の時間が不十分であると指摘し、年齢に応じた包括的な性教育が学校教育課程に適切に組み込まれることを勧告しました。また、保険・避妊に関しては、さまざまな避妊法へのアクセスが欠如していることを指摘し、全ての女性と女児に手ごろな価格で現代避妊法への十分なアクセスを提供することを勧告しました。更に、16歳と17歳の女児が避妊法を利用する際に、親の同意を得る要件を撤廃することを勧告しました。
それに加えて、保健・中絶に関しては、人工中絶へのアクセス制限や配偶者の同意書が必要な点、また中絶にかかる法外な費用についても指摘され、中絶の合法化、配偶者同意の要件の削除、経口中絶薬を含む安全な中絶サービスへのアクセスの強化を勧告しました。
HRN 伊藤和子
4名のプレゼンターのお話を聞いた後、HRN副理事長の伊藤和子よりお話がありました。伊藤は、CEDAW勧告に対する日本政府の建設的な対応の欠如を強調しました。日本政府がCEDAW勧告に対して行った対応として、「政府がCEDAWに対してOHCHRに対する任意拠出金の使途からCEDAWを除外すること」と、「本年度予定のCEDAW委員の訪日プログラムの実施を見合わせること」を発表したことを指摘しました。そして、日本政府が国際連合による勧告を受け入れ、適切な対応を行うように活動を続けていく必要があると述べました。
質疑応答
本ウェビナーには、多くの参加者からゲストスピーカー4名への質問が寄せられ、各スピーカーが回答しました。質問内容は、再婚に伴う子供の姓への議論の欠如やジェンダー平等を基にした選挙行動についてなど多岐にわたり、それぞれゲストスピーカー4名が回答しました。
閉会の挨拶
HRN副理事長の後藤弘子より閉会の挨拶があり、各ゲストスピーカーからもメッセージをいただきました。