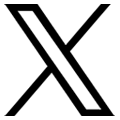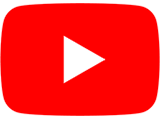2015年11月4日、東京大学駒場キャンパスにて、東京大学総合文化研究科と認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウの主催で、記録映画『太陽がほしい』の上映会と、班監督を招いてのトークが行われました。
以下、イベントに参加したインターンの報告をご紹介します。
『太陽がほしい』は、班忠義監督が1992年より慰安婦とよばれた中国人女性たちに行ってきたインタビューを記録したドキュメンタリー作品であり、戦後の日中関係の描写や、この問題をめぐる戦後の活動なども織り交ぜながら、多面的にこの問題を考えようという趣旨になっています。
この映画では、ひとくくりに「慰安婦」とされてきた女性たちの多様な被害のあり方はもちろんのこと、彼女たちが戦後になって中国政府・社会から如何に扱われてきたか、また何をどのように考えて生き、如何なる活動に取り組んできたかが鮮明に描かれています。若いときの被害の深刻さにより心身ともに傷を負っただけでなく、その後も「日本人の手先」と社会に見なされ差別が続いていました。さらに中国政府自身も、日本との協力を選んで復興を遂げ、また天安門事件後の制裁解除も日本が最初であったことから、「慰安婦問題」は国家的タブーとなっていきます。「被害者」としての彼女たちを支援しようと立ち上がった中国の市民も弾圧を受けるなど、この問題に取り組もうとすればするほど新たな問題が立ちはだかる実態が描き出されていました。
そして現在最も逼迫した問題は、被害者の高齢化と記憶の風化です。映画の最後ではドキュメンタリーの主人公たる女性たちが近年相次いで亡くなったことが記され、この映画が最後の生きた証言を記録したものであることを物語っています。長編映画にも関わらず、上映会後のトークでは、この点に関する質問も含め、白熱した質疑応答が見られました。
トークでは、まず班監督がご自身の来歴を語りました。残留孤児の人に出会い、戦争の深刻さを実感し、日本に留学されたこと、また戦後50周年の時に、戦争を深刻にとらえる風潮が薄れていることに危惧を感じて本映画の取材を始められたとのことでした。両国の政治状況について、日本市民には憲法が定着したと感じられること、それに対して中国ではこの映画も半分くらいはカットしなくてはならないことを率直に述べられました。またこの映画が日中双方の市民レベルの動きによって生まれたことを大変喜ばしく思うとのことでした。
続いて、東京大学総合文化研究科国際社会科学専攻の阿古智子准教授の司会のもと、同研究科地域文化研究専攻の外村大教授のトークが始まりました。外村教授は在日朝鮮人史、近代日本をめぐる人の移動、また植民地期の朝鮮社会をご研究されています。外村教授は、外交問題として捉えられがちな戦争をめぐる問題について、実際は民衆が近代化の中で如何に動いてきたかという問題だという視点が大切だと述べられました。普段東京大学の1,2年生に対して日本近現代史等を教えるなかで実感されるのは、現代の社会においてある程度の「階層分化」が進み、恵まれた環境にいることが多いとされる東京大学の学生に、「民衆の視点」、「被害者の視点」を気付かせるのが難しいということだそうです。その意味で、今後このような映画会に学生が増えることを期待されるとのことでした。さらに、日本社会が変化し、慰安婦をめぐる世論も右傾化していることへの危惧を表明されました。
質問者の中には、東京大学の学部生・院生、中国からの留学生など若い世代も目立ちました。戦後に生まれた世代としてこの映画に如何に向き合うべきかという質問に対して班監督は、民主主義のもと加害国のリーダーを選ぶ立場にいる意味で、決して戦後世代は無関係でないこと、また人間の罪を考えるという意味では、人類にとって普遍的な課題であることを指摘しました。
班監督自身がこの映画を撮影する際に苦労した点についての質問もあり、信頼関係を築くためにも、貧困・病気で苦しむ女性を病院へ連れて行くなどの「救助」を優先したことなどにも触れられていました。鋭い質問もあり、映画のなかで「河野談話」や「女性のためのアジア平和国民基金」に触れていなかったことの是非も問われました。これに対して外村教授は、被害女性たちに実態としてそれが「届いていない」ことを把握する大切さを指摘し、また班監督は、根本的な謝罪のない基金は、かえって貧困のためだけに「あげる」という侮辱になりかねないと述べました。最後に、班監督は、自身が中国の当局や日本の右翼を前にどのように突き進むかを問われ、何があっても勇気をもって取り組む決意であると述べており、印象的でした。
ヒューマンライツ・ナウの伊藤和子弁護士は、当時の実態の残虐性を実感するのとともに、現代に危機感を覚えることも指摘しました。映像途中で出てきた慰安婦の存在を否定するような論調が、当時は少数派であったにも関わらず現在は国の主張にも浸透してきており、今後言論の自由を行使して取り組みたいと述べました。
最後に、この機会に参加して感じたのは、外交問題の俎上に載せられた「慰安婦問題」を、「一人の人間」の問題として捉えなおしたとき、今まで如何に何も考えていなかったかということでした。そしてこの視点に立った瞬間、一人の人間という立場では、日中の市民は対立するどころか、今後ますます協力できるのだという可能性をも感じました。青春を奪われ、一生残る深い傷を負い、また戦後も差別や貧困に苦しみながらも生きた女性たちの強さは、国籍も性別も問わず学ぶべきことが多いと思います。起き上がれなくなった晩年になっても「真理を取り戻さねばならない」と言い、一方で「寝たきりになっても生きていてごめんなさいねえ」と言う心の柔軟さは、私たちが最初に見習うべきものなのかもしれません。(文責:高橋知子)