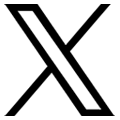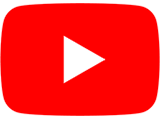国連人権高等弁務官事務所の用意する日本の人権状況の要約文書のための提言書
2008年2月7日
国連人権高等弁務官事務所 御中
ヒューマンライツ・ナウ
Asian Legal Resource Centre
Ⅰ 一般的懸念事項
1. 日本の現状と国際基準との深刻な隔たり
日本は、自由権規約、社会権規約、拷問等禁止条約、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、子どもの権利に関する条約、といった国際人権条約を批准している。しかし条約に定められた義務の履行は、広い範囲で立ち後れている。日本の現状と国際基準との間には、以下に詳述するとおり、深刻な隔たりがある。
2. 貧弱な条約義務の履行
人権条約の各委員会から繰り返し勧告を受けているにもかかわらず、日本はそれら勧告の多くを看過しており、勧告を実行する政治的意思がほとんどみられない。
勧告を受けている主な領域は、刑事司法、死刑制度、婚外子差別などである。さらに、各条約委員会への定期報告は、多くの場合、提出が遅滞しており、自由権規約委員会、拷問禁止委員会への報告など、5年以上遅れているものもある。
3. 個人通報
日本は、主な人権条約の選択議定書のいずれも批准しておらず、国民が個人通報する道を阻んでいる。日本は自国の人権状況を国際的視点での検討から遠ざけ、かくして条約義務の履行を怠っている。
4. 国内人権機関(NHRI)の不在
日本には、パリ原則に則った国内人権機関がない。2002年、政府は国内人権機関の設立条項を含む「人権擁護法案」を国会に提出した。しかし、内容は、機関の独立性の点など、パリ原則に合致していない不備がある。また国会を通過していない。その後、新たな立法を提案する動きが政府にあるが、パリ原則について深刻に考慮していない。
5. 司法制度の問題
日本における裁判のほとんどが、国際人権基準を無視しているか、理解が不十分である。国際人権条約に照らして判決が下されることは、極めて稀である。
Ⅱ 個別的懸念事項
1. 刑事裁判の公正さ
1-1 起訴前勾留と取調べ
1-1-1 日本では起訴前勾留はたいてい23日間に渡り、「代用監獄」と言われる警察の留置施設においてなされ、そこでは警察が被疑者の日常生活をコントロールする権限を握っている。起訴前勾留において、司法的抑制は単に形式的なもので、起訴前保釈制度もない。拘束された被疑者は、閉鎖され、鍵を掛けられた密室で、取調受忍義務を課されて取調べを受け、取調べ状況を電子的にモニターするシステムは存在しない。取調べの間、弁護人の同席も認められていない。取調べの時間帯や長さを規制するルールはない。自由権規約委員会はこのような起訴前勾留の慣行に深い懸念を表し、日本の起訴前勾留制度が、規約第9条、第10条及び第14条の規定に従い、速やかに改革がされるべきことを、強く勧告した。しかしながら、今日にいたるまで、上記の状況に変化はない。
1-1-2 日本の刑事裁判制度は「人質司法」と呼ばれている。警察が被疑者を人質として、自白を得ようとするからである。このような状況は、基本的人権を当然危うくするものであり、警察による被疑者の権利侵害の可能性を高めるものである。事実、警察の取調べは、自白を強要し、間違った有罪判決を導く、深刻な不正行為に繋がっている。
例をあげると、2003年の鹿児島選挙買収事件で13人が逮捕されたが、その際、警察による不当な取調べが行われた。警察は、被疑者に父親や祖父の名前を記した紙を踏みつけさせる「踏字」の強制や、取調べの最中に怒鳴り、「地獄に送ってやる。」「死刑にしてやる。」「自白しないなら、家族を逮捕する。」などと脅すというような、不正行為をおこなった。この裁判のすべての被告人は2007年に無罪が確定した。(志布志事件)。また、2007年には警察に虚偽の強姦罪の自白をして有罪となった人の無罪が判明し、再審で雪冤した富山の例がある。取調べ中に警察が被疑者に不正行為を行ったという訴えは、メディアの扱いも増加している。2004年以来、メディアは51件の不正な取調べを告発している。
1-1-3 このような不正行為を防ぐために、自由権規約委員会は、「警察留置場すなわち代用監獄における被疑者への取調べが厳格に監視され、電磁的記録により記録されるべきこと」を強く勧告した(1998)。にもかかわらず、取調べ過程の全面的な録画・録音制度は日本に未だ導入されていない。2007年現在、日本の一部地域で、検察官らが自らの判断に基づいて、検察官に対する被疑者の自白を部分的に録画する試みが始まっている。しかし、これによって、取調べにおける人権侵害や虚偽自白のすべてのリスクがなくなるわけではない。かえって、検察官が自らの裁量によって自白の一部のみを録画するやり方により、取調べ全体の事実を隠蔽し、司法判断をおこなう者の誤解に導き、間違った有罪判決を下すことになる危険性をはらむ。取調べの全面可視化が必要である。
1-1-4 上述の起訴前勾留と取調べの問題は、司法判断も責任の一端を負っている。自由権規約委員会が懸念するように、「刑事事件の有罪判決の多くが自白を根拠にしており」(1998)、裁判官は自白に頼りすぎる傾向がいまだにある。例えば一人の死刑囚は1961年に自白し、1969年に死刑判決を受けたが、このケースについて、2005年になって、高等裁判所が、科学的立証に基づき再審開始を決定した。ところがその1年後、別の高等裁判所はこの件における自白の存在を強調して、再審開始決定を取り消した。(名張事件)
1-2 公平な裁判を受ける権利
1-2-1 日本の有罪判決の比率は99.8%であり、「推定無罪」(自由権規約14条2項)の原則が日本で現実に保障されているのか、深刻な疑いが存在する。
1-2-2 自由権規約委員会は、「規約第14条3項に規定された保障に従い、締約国が、防禦権を阻害しないために弁護側がすべての関係資料にアクセスすることができるよう、その法律と実務を確保すること」を勧告した(1998)。この点では、2004年の刑事訴訟法の改正により、検察官による弁護側に対する事前証拠開示の条項が設けられた。しかし、検察官が絶対的な開示義務を負う範囲は限定されており、開示許可条件があいまいである。そのため、裁判官が条文解釈をつうじて、証拠開示を命ずるか否かの広範な裁量権を有することになる。そしてなにより、改正法には検察側に、被告側にとって有利な証拠を開示することを義務づける規定がない。さらに、再審については、死刑囚の事件も含めて、有罪判決を受けた者が、再審請求をし、無実を証明するための証拠開示を認めるルールが存在しない。
2. 死刑
日本政府は死刑廃止または死刑執行停止に向けて、何の方策も立てていない。逆に死刑判決は増加している。2007年には、46人の被告が日本の裁判所から死刑を宣告され、この数は1980年以来もっとも多い。2003年から死刑囚は2倍になった。2003年は50人ほどであったが、2007年には100人以上である。
3. 拷問
近年、日本の刑務所のいくつかで、拷問の慣行があることが明らかになった。2001年、名古屋刑務所において、多数の受刑者が臀部への高圧放水で負傷し、ひとりが死亡した。2007年には、徳島刑務所で医師による拷問が明るみに出た。同医師は受刑者の肛門に器具を挿入し、執拗に痛めつけた。広範囲に行われたこの徳島刑務所での拷問によって、7人が死亡し、ひとりが自殺を図った。
4. 経済的、社会的、文化的権利の根本的な義務違反
日本は、基本的な食糧、医療、住居といった、経済的、社会的、文化的権利を保障するための最低限の義務を果たしていない。
4-1 日本は、最低限の生活を保障するという根本的な義務を果たすべく、社会的に最も困窮する人々のために「生活保護制度」を運用しているが、現在全国で、地方自治体職員が、生活保護の申請を拒否したり、申請者に申請を諦めるよう強く勧めたりする現象がひろがり、その結果重大な結果を生んでいる。例えば、北九州では、2005年に68才の男性が、そして2006年には56才の男性が、いずれも生活保護申請を拒否された後に餓死している。2007年には52歳の男性が生活保護の支給を止められた後に餓死した。厚生労働省は、このような生活保護行政の慣行を止めさせるための適切な方策を立てていない。むしろ、「不正需給」を減少させるように強く指導することによってこの慣行を助長している。
4-2 さらに日本は、弱者に対する社会保障措置について、後退的措置をとっている。かつては、70才以上の生活保護世帯は、さらに老齢加算給付を受けられたが、2004年に政府は老齢加算給付の減額を始め、2006年には全面廃止した。また、母子家庭の生活保護世帯にも加算給付があるが、この加算給付も2005年から減額されている。
4-3 ホームレス
日本には約2万人のホームレスの人々がいる。ホームレスは、定まった住居を持たないため、職業安定所に登録してサービスを利用することができず、また、老齢年金も障害者年金も生活保護も受けられない。政府や地方自治体の支援はシェルターや住居を提供するに留まり、職業斡旋は含まれていない。こうしてホームレスの自立は困難に直面しており、路上生活が長引く傾向にある。
5. 差別
5-1 各条約体(自由権規約委員会、社会権規約委員会、女性差別撤廃委員会、子どもの権利委員会)からの度重なる勧告にもかかわらず、婚外子への差別が、特に国籍、戸籍、相続権について存在している。民法第900条4項は、明確に婚外子の相続権を差別しているがいまだ改定されず、2004年最高裁は当該条項について憲法違反は認められないと判断している。国籍法第2条は婚外子の日本国籍を認めていないが、これもいまだ改定されず、最高裁は2002年憲法違反のないことを認めている。
5-2 自由権規約委員会の懸念にもかかわらず、婚姻の解消または無効から6ヶ月以内は、女性に再婚を認めないという差別的な法律がいまだ存在する。
5-3 先住民であるアイヌの人々は、教育や雇用をはじめ、さまざまな社会的差別を受けており、土地所有権も保護されていない。2007年9月国連総会において、先住民の権利宣言が採択されたが、日本政府は、アイヌの人々を権利を守るべき先住民と認めていない。
5-4 外国籍の人々
5-4-1 人種差別撤廃条約委員会の懸念にもかかわらず、人種差別を禁止するための法律が日本にはない。
5-4-2 子どもや学生の間を中心に、在日コリアンへの暴力が続いている。この種の行動は、日本と北朝鮮の間に外交問題が起こったとき、増大する傾向がある。日本政府は、このような行動に反対し、再発を防止するための確固たる対策をとることをできずにいる。
5-4-3 学校教育法においてコリアン系の各学校が、正規の「学校」として認められておらず、学生が政府や地方自治体から金銭的援助を受けるときなどに、在日コリアンの学生は不平等な扱いを受けている。
5-4-4 出入国管理及び難民認定法第26条は、外国人が出国し在留資格を失わず再入国するには、再入国許可が必要であるとし、許可を与えるかどうかは法務大臣の裁量としている。この規定のために、日本に生活拠点をおく在日外国人2世3世が出国した場合、再入国できない可能性がある。
5-4-5 退去強制手続について適正手続が十分に保障されていない。退去強制令書発布に際しての違反調査にあたっては、閉鎖された部屋での取調べが行われ、モニターも録画もされていない。日本政府は、しばしば、退去強制令書が発布された外国人を、当該処分の適法性を争う裁判の法定出訴期間が過ぎるのを待たずに、強制送還している。この不正行為は裁判を受ける権利を明らかに侵害している。
5-4-6 出入国管理及び難民認定法第6条は、テロリズムに対抗する手段として、米国のUS-VISITプログラムにならい改定され、外国人および特別長期滞在者を除く再入国者すべてに、指紋情報、顔面像、その他個人識別情報の提供を義務づけた。この制度は情報採集方法、処理方法、利用の範囲などに何の制限もないまま、導入された。
5-4-7 難民認定申請者と難民
出入国管理及び難民認定法によると、難民認定は法務省管轄の入国管理局でなされ、法務大臣の判断に任される。中立的で公平な判断を確保するためには、難民申請に対する判断をするための、政治的に独立した組織が設立されなければならない。申請者は生活保障や健康保険を受ける権利が与えられていないだけでなく、就労が禁止されているため、必然的に不法就労に携わるしかない。また、日本には、難民認定申請者の個人情報を秘密にしておくよう、公務員を規制する法律がない。政府が、申請者の母国に、情報を漏らす場合もあった。
5-5 さらに、被差別部落出身者、女性、障害者に対する構造的差別がひきつづき存在している。
6. 思想、良心、表現の自由
6-1 思想と良心の自由(自由権規約第18条)も脅かされている。近年、いくつかの地方自治体が、公的式典において「日の丸」の旗のもとで、国歌である「君が代」を歌うよう、教職員に強制している。「日の丸」「君が代」はいずれも、第2次世界大戦までの大日本帝国の象徴であることから、その是非については国内で議論の分かれる問題である。特に東京都では、388人の教職員が、君が代を歌うこと、日の丸旗の前で起立することを拒んだために懲戒処分を受けた。2007年2月、最高裁は、君が代のピアノ伴奏を拒んだ音楽教師に対する戒告処分について、すべての国民に思想と良心の自由を保障した憲法第19条に反しないと判断した。教師にこのような強制が許されると、間接的に生徒にも義務づけられることとなる。そのため、子どもたちの「干渉されることなく意見を持つ権利」(自由権規約第19条、1項)も脅かされている。
6-2 表現の自由については、単に政治活動をしただけで、有罪とされた例が近年あいついで存在する。日本では、公務員による文書配布などの政治活動や選挙運動の一環として行われる戸別訪問が禁止されており、刑事罰の対象とされている。裁判所はこうした制限について、憲法違反・自由権規約違反の主張をいずれも退けている。
7. 人権侵害の被害者に対する、実効的救済措置に対する国家の義務
日本政府は第二次世界大戦中に日本軍が犯した、強制労働や性奴隷制などの重大な人権侵害行為の被害者に対する個人補償を行っていない。日本の司法は、政府の主張に基づき、繰り返し、被害者に対する損害賠償をおこなう日本政府の法的責任の存在を否定してきた。2007年4月、最高裁は従軍慰安婦および強制労働に対する補償請求権を否定する判断を相次いで下した。日本政府は人権侵害の包括的な調査、責任者の特定、起訴、被害者の補償のいずれの措置行っていない。さらに政府は再発を防ぐための教育的手段をとっていない。政府官僚や先の総理大臣などは、性奴隷制の存在すら否定する発言を公然と行い、このような行為が被害者の心の傷をさらに深くしている。
付属書類
Ⅰ 一般的懸念事項
2. 自由権規約委員会は1998年、「委員会は、3度目の定期報告を考慮した後の勧告の大部分が履行されていないことを遺憾に思っている」と明確に述べているが、それ以降状況は変わっていない。
5 司法制度における問題
最高裁判所は以下のとおり、人権条約体の勧告に反する一連の判決を下している。
最高裁判決(1995年7月5日、2000年1月27日、2003年3月28日、2003年3月31日および2004年10月14日)
最高裁は、非摘出子の相続権を明らかに差別している民法第900条第4項は平等権を保障する憲法第14条に反しないとした。これは1998年の自由権規約委員会の勧告に反するものである。
最高裁判決(2002年11月22日)
最高裁は、非摘出子は日本国籍を獲得できないと定める国籍法第2条は合憲であるとした。
最高裁は、非摘出子は、国籍法第2条の解釈のもと、父親が日本人であったとしても日本国籍は得られないと判断し、こうした区別は、合理的なものであり違憲ではないとした。この結論は1998年の自由権規約委員会の意見に反するものである。
この判決の前に、大阪高等裁判所は、自由権規約の締約国は自由権規約委員会の一般的意見や政府報告書に対する最終見解には、法的に拘束されないと言明した。(大阪高裁判決(1998年9月25日))。
最高裁判決(1993年3月2日、2000年3月17日)
最高裁は、公務員のストライキの全面禁止について、ILO条約第87号、社会権規約第8条に反しないと判断した。この判断は、ILO専門家委員会の適用に関する意見、並びに、経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の勧告及び意見に矛盾する。
最高裁判決(1993年5月10日)
最高裁は、計200日間の断続的な(一度につき50日間まで)隔離拘禁は自由権規約第7条および第10条に抵触しないとした。
Ⅱ 個別的懸念事項
1-1-1 起訴前勾留
2 関連する1998年の自由権規約委員会の意見は以下のとおりである。
21.自由権規約委員会は、起訴前勾留は、警察のコントロールのもとで23日間もの長期間にわたり継続することが多く、司法の監督下に迅速かつ効果的に置かれない点、被疑者がこの23日の間、保釈される権利を与えられていない点、取調べの時刻と時間を規律する規則がない点、勾留中の被疑者に助言し、援助をする国選弁護人がない点、刑事訴訟法第39条第3項に基づき弁護人の接見には厳しい制限がある点、取調べが被疑者によって選任された弁護人の立会いなしに行われる点で、規約第9条、第10条及び第14条に規定する保障が完全に満たされていないことを深く懸念する。委員会は、日本の起訴前勾留制度が、規約第9条、第10条及び第14条の規定に従い、速やかに改革がされることを、強く勧告する。
23.委員会は、代用監獄制度が、捜査を担当しない警察の部局の管理下にあるものの、別の機関の管理下にないことに懸念を有する。これは、規約第9条及び第14条に基づく被拘禁者の権利について侵害の機会を増加させる可能性がある。委員会は、日本の第3回報告の検討後に発せられた、代用監獄制度が規約のすべての要請に合致されるべきとした勧告を再度表明する。
25.委員会は、刑事裁判における多数の有罪判決が自白に基づくものであるという事実に 深く懸念を有する。自白が強要により引き出される可能性を排除するために、委員会は、警察留置場すなわち代用監獄における被疑者への取調べが厳格に監視され、電磁的手段により記録されるべきことを勧告する。
(2) 刑事訴訟法第60条に基づき、警察は逮捕状によって被疑者を最長3日間まで拘束することができる。裁判官は、逃亡のおそれまたは罪証隠滅のおそれが疑われるときには、検察官の請求により被疑者を10日間以内で勾留する権限を与える勾留状を発布することができる。勾留は、10日間まで延長することが出来る。
しかし、裁判官により勾留請求が却下される割合は全体の5%に満たない。1996年には、起訴前勾留状を裁判官が却下した割合は0.31%であり、2006年は3.4%であった。( http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/B18DKEI15~16.pdfを参照のこと)
近年、確かに却下の割合は増加しているものの、被疑者が勾留されないことは依然として稀である。
1-1-3 身体拘束下での全面的な取調録音・録画制度を導入することについて、主に反対しているのは、警察と法務省である。
1-1-4 名張事件は、司法判断が極端に自白に偏重していることを明確に示している。名張事件では、奥西再審請求人は、警察での40時間以上の取調べの後に自白した。
2006年、名古屋高裁は「その経緯から明らかなように、身柄が拘束される以前の任意の取調べの過程で、自らの犯行であることを自供したことが認められる」、「これだけの自白を任意に行ったのであるから、通常は、請求人の体験に基づく真実の自白であると考えられる。仮に請求人が犯人でないとすれば,請求人は,上記のような犯行のストーリーを創作しあえてうその自白をしたことになるが,そこまでしてうその自白をしたのだとすればそれは何故か,うその供述をしなければならない特別の事情があったのか,これらの点について,納得できる理由がなければならない。」
とした(2006年12月26日)。
奥西氏は、1964年に第一審で無罪となった。しかし、1969年に、名古屋高裁で逆転して有罪となり死刑が言い渡された。1972年、最高裁判所は、この高裁判決を支持し、死刑有罪判決が確定した。現在81歳の奥西は1969年から死刑棟におり、一貫して無罪を主張している。
詳細はウェブサイトを参照。 http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2007/2568/
1-2-2 証拠開示
(1) 関連する1998年の自由権規約委員会の意見は以下のとおりである。
26.委員会は、刑事法の下で、検察官には、公判で提出予定の証拠を除き、捜査の過程で収集した証拠を開示する義務がなく、弁護側には手続の如何なる段階においても証拠の開示を求める一般的な権利が付与されていないことを懸念する。委員会は、規約第14条3に規定された保障に従い、締約国が、弁護側の防禦権を阻害しないために、弁護側がすべての証拠資料にアクセスすることができるように、法と実務を改めることを勧告する。
(2) 証拠開示に関する新たな規定(刑事訴訟法第316-14から27条)の概要は以下のとおりである。
1) 検察官は証拠開示の一般的な義務を負う。
取調請求をした証拠書類または証拠物
検察官が取調請求した証人の人物の氏名と住居
証人が公判期日に供述すると思料する内容が明らかになる供述録取書等
2) 検察官は被告人からの開示の請求があった場合、請求が下記の条件を満たす場合には、以下の情報を開示するものとする。
[条件]
a. 検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められる場合、および
b. 検察官が、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるとき、
[情報]
a. 供述調書
b. 科学的試験、実験の文書
c. 有罪立証のため、検察官が証人として尋問を請求することを予定している者の関連供述調書
d. 被告人の供述調書
e. 取調状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官、警察官が作成を義務付けられている書面
3) 被告の特定の証拠開示請求があった場合に、検察官が、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるとき、検察官は被告の主張に関連する証拠を開示するものとする。
4) 裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、弁護人または検察官による請求に基づいて、開示が必要と認めるときは、開示に関する決定を下すものとする。
2 死刑
(1)自由権規約委員会は、1998年に、日本が死刑を廃止するための政策を採ること、死刑が最も重い犯罪に限定されることを勧告した
(2)現職の鳩山法務大臣は、大臣の命令なく有罪の犯罪者を自動的に処刑することを提案し、公に「死刑廃止は日本で受け入れられていないと考える」と明確に述べた。現在も日本では、死刑執行は常に突然行われ、起訴された者とその家族に対し、事前の通知はなされていない。
2007年12月、本人またその家族に対する事前の通知なく、75歳を超える人を含む3人が突然処刑された。
(3)2007年12月7日の国連ニュースによれば、人権高等弁務官のルイーズ・アルブール氏は日本における上記死刑執行を非難し、死刑へのアプローチを見直すよう日本に求めた。ルイーズ・アルブールは、「この慣習は国際法上問題があり、私は日本にこの点でアプローチを見直すよう求める」、「高齢者にこのような刑を執行することに、どのような目的の正当性があるのか、理解するのは困難であり、少なくとも人権の観点から、こういった行動を控えるよう日本に求める」と述べた。
4.経済的、社会的、文化的権利の根本的な義務違反
4-2 後退的措置
さらに、母子・父子家庭に対する育児手当を最大50%まで削減する法律が2002年に成立し、2008年に発効する予定とされていた。多くのシングルマザーがこの法律を批判したため、政府は法律の実施を暫定的に停止することを決定した。しかし、現在のところ、政府にはこの法律を改正する計画はない。
社会権規約の一般的意見が述べるように、「あらゆる恣意的に後退的政策はもっとも慎重に考慮をすべきであり、最大限利用できる資源を使うという前提で、規約に規定される権利の全体を考慮し、完全に正当化される場合にのみ許される」。日本の場合、本文に記載したようなもっとも弱い立場の人々に対する後退的政策はいかなる意味においても正当化できない。
5.差別
5-1 非摘出子に対する差別
(1)国籍法(抜粋)
国籍法(昭和25年法律第147号、改正 昭和二十七年七月三十一日 法律第二百六十八号、昭和五十九年五月二十五日 法律第四十五号、平成五年十一月十二日 法律第八十九号、平成十六年十二月一日 法律第百四十七号)
(この法律の目的)
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を
有しないとき。
(準正による国籍の取得)
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳
未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の
出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民で
あるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出
ることによって、日本の国籍を取得することができる。
5-4 外国籍の人々
5-4-2 在日コリアンに対する暴力的な行動は、北朝鮮政府が2002年9月公式に日本人拉致を認めた直後に、また2006年7月に北朝鮮政府が日本の領空にミサイルを発射したとき、顕著に起こった。暴力的な行動には、「朝鮮人を殺す」、「ゴキブリは日本から出て行け」などの直接またはインターネットを通じての脅迫、満員電車内で女子学生の制服を切る、公衆の面前で在日コリアンの学生を蹴るといったものが含まれる。
5-4-5 裁判を受ける権利を侵害する政府の不正行為の例として、2007年1月にバングラディッシュ人8人が退去強制令書発布の3時間後に日本から退去させられた事例がある。このうち、何人かははっきりと、弁護士に連絡を取りたいと述べたが、出入国管理官は手錠をかけ強制的に空港へ連行した。このケースは現在(2008年2月)東京高裁で審理中である。
5-4-7. 難民認定手続のための独立機関に関しては、出入国管理及び難民認定法が2004年に改正されたことにより、参与員制度の導入がなされたが、この制度は問題の解決にはなっていない。参与員は、民間の有識者・学識者から構成され、難民認定の異議申立手続の中で、法務省に対して意見を述べることになっているが、その意見には拘束力がない。また、参与員は法務大臣に任命されるため、参与員が政府から組織的に独立していないことも批判されている。さらに、参与員の事務作業は入国管理局に委譲されている。任命手続には透明性がなく、現在までに国連難民高等弁務官事務所が参与員の候補に上げた8人のうち、法務省に任命されたのは4人に留まる。 法務省は、難民申請者の個人情報を以下のとおり、出身国に開示したことを認めた。法務省は、難民認定手続において入国管理局に難民申請者が提出した文書の信用性を確認するなかで、このような漏洩が生じた、としている。
2000年 エチオピア1件、イラン1件およびカメルーン1件
2001年 アフガニスタン2件、イラク1件
2002年 アフガニスタン4件、トルコ3件、エチオピア1件、チュニジア1件、スーダン4件
2003年 アフガニスタン5件、イラン5件、トルコ7件、ミャンマー4件、パキスタン1件
さらに、2004年6月から7月、日本の法務省職員がトルコ共和国を訪問し、トルコの法務省の職員、政府検察官および地方知事と面会した際、彼らに難民認定手続中の難民申請者が提出した逮捕令状が真正であるかを、現に逮捕令状をトルコ当局に見せた。その後、法務省訪問団はトルコの治安部隊を伴って、地方の村に住む難民申請者の家族を訪問した。治安部隊の目の前で、訪問団は、家族に対し、なぜ日本にいる難民申請者がトルコを離れたのかを質問した。国連難民高等弁務官事務所東京事務所、日本弁護士連合会、アムネスティ・インターナショナルおよびその他関連団体はこれらの不当行為を厳しく非難している。
6 思想、良心および表現の自由
6-2 2006年6月29日、東京地裁は、政党のビラを配ったとして公務員の男性を有罪とした(堀越事件)。
2007年9月7日、福岡高裁は選挙活動中に個人宅を訪問したとしてある男性を有罪とした(大石事件)。最高裁は、2008年1月28日、選挙活動中の戸別訪問を犯罪とすることは憲法違反でも自由権規約の違反もないとして、大石氏による上告を棄却した。
7 実効的な救済措置
慰安婦の問題に関しては、1995年に政府は、民間から資金を集め、各被害者の補償にあてる「アジア女性基金」(AWF)を設立した。しかし、多くの被害者は受け取りを拒否してきた。AWFはすでにその活動を終了しており、現在、性奴隷制度の被害者を救済する制度はなんら提供されていない。
国連拷問禁止委員会(2007)は「戦時性奴隷の被害者は、締約国が公式に事実関係を否定し、他方で事実を隠蔽もしくは非公開にし、拷問行為に責任のある者を刑事訴追せず、また犠牲者および被害者に対して十分なリハビリテーションを提供していないことにより、継続的な精神的虐待を受け、また精神的外傷を新たに与えられている。」と述べている。現在のところ日本政府はこのような状況に対していかなる対策も取っていない。
英文は国連人権高等弁務官事務所のウェブサイトに掲載されています。
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session2/JP/HRN_JPN_UPR_S2_2008
_HumanRightsNowAsianLegalResourceCenter_uprsubmission_JOINT.pdf